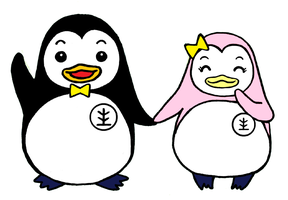特別寄稿(令和2年1月1日発行練馬区保護司会報第245号に掲載)
18歳、19歳は「おとな」か ―法制審議会で議論されていることー
後藤 弘子(第5分区保護司) 千葉大学大学院専門法務研究科教授
「おとな」と子どもの線引き
2016年に選挙権年齢が引き下げられたのに続いて、2018年民法が改正され、2022年から成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられることになった。しかし、「おとな」として評価される年齢は、実は均一ではない。
民法の成人年齢である20歳に達していなくても、有効な遺言(15歳)を残すことや結婚(女性16歳、男性18歳。これについて、2022年から18歳に統一される。)すること、車を運転すること(18歳)など、子どもの発達段階に応じて、事柄ごとに適切な年齢が設定されている。
なお、2022年になっても、飲酒や喫煙可能年齢や馬券の購入などは、20歳のままであり、「おとな」の年齢の統一性はないままである。
そんな中で、少年法の成人年齢も引き下げるべきだという議論が続いている。2017年3月に、重要な法改正の際に必ず開催される法制審議会(法務大臣の諮問機関)で、少年法の年齢の引下げの議論が開始された。
法制審議会での議論
今回の法制審議会では、少年法の成人年齢を18歳に引下げることのほか、「非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるため」の刑法や刑事訴訟法の制度改正についても、議論されている。
2019年10月30日に開催された第19回会議で、これまでどのような議論がされているのかがまとめられている(「部会第8回会議から第18回会議までの意見要旨(制度・施策関係)・(年齢関係)」(法務省HPで入手可))。
それによると、現在刑務作業が義務付けられている懲役刑とそうではない禁錮刑に分かれているが、それを統一する新自由刑の創設、保護観察付き執行猶予中の再犯に再度の執行猶予を科す制度の導入、罰金に対する保護観察付き執行猶予など、保護観察制度にとっても重要な改正が議論されている。また、少年の成人年齢が引き下げられた場合に、18歳、19歳の年長少年(以下単に「年長少年」という。)に対し、新たに導入すべき「若年者に対する新たな処分」についても、検討されている。
来年(2020年)2月には、一定の結論が出されるといわれており、もし現在の議論が法制度化されれば、更生保護にとっても2008年施行の更生保護法以来の大改革になるであろう。
はじめから年長少年は問題だった
今回の法制審議会の議論で最も注目を集めているのが、少年法の成人年齢の引下げである。少年法が施行されたのが1949年で、今年は、少年法施行70周年の記念の年であるが、その当初から、少年の成人年齢が20歳のままでいいかが問題とされていた。
1922年に施行された旧少年法は、少年の年齢が18歳未満とされていたことから、現行少年法は附則68条で「この法律施行後2年間、第2条第1項の規定にかかわらず、少年は、これを18歳に満たない者とし、成人は、これを満18歳以上の者とする。」とし、制度の移行の混乱を避けようとしていた。
この適用が終了する1951年に、法務省(当時は法務庁)は、年長少年については、検察官が必要だと思った時だけ家庭裁判所に送致する「検察官先議制度」の導入を目指して「少年法改正構想」を明らかにするなど、少年法は、常に、年長少年を「おとな」として扱う圧力にさらされてきた。
その後、1970年には、年長少年を「青年層」として検察官先議とする制度が法制審議会で議論されるも、最高裁判所や弁護士会の反対を受け、1977年の少年法改正中間報告を最後に頓挫することで、年長少年をより「おとな」として扱う制度の導入は見送られた。さらに、2000年以降4回の少年法改正を経ても、年長少年を少年として扱い、少年法制の枠内で扱うべきだ、という少年法の基本的な理念は支持され続けた。
国法の統一性?
40年ぶりに、年長少年を少年法の枠組みから外すという今回の法制審議会における議論の背景には、少年非行の凶悪化や増加といった、非行少年が社会に与える影響があるわけではない。周知のとおり、少年非行は、減少の一途をたどり、殺人や強盗といった凶悪犯罪も減少し、現行少年法施行後最低の数となっている。また、非行少年に対しては、刑罰で臨むより、発達段階に応じた教育を行ったほうが非行を減らすという目的をより達成できる、ということについては、専門家の間では常識となっている。
今回、年長少年を少年法の枠組みから外すべきだという議論がなされ、法改正へと向かおうとするその背景には、最初に述べた公職選挙法や民法の改正がある。選挙権年齢や民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたので、「国法の統一性」を重視して、少年法の成人年齢も引下げるべきだという発想は、一定の合理性を持つ。
けれども、最初に見たように、「おとな」年齢の統一性はそもそも存在しない。また、法律の目的によって、当然に「おとな」として評価される年齢も異なる。「国法の統一性」を重視せよという要請だけでは、少年法の成人年齢を下げる理由としては十分ではない。
ではなぜ、公職選挙法や民法の改正が少年法の改正を後押ししているのか、法制審議会の議論から少し見てみよう。以下の引用は、第19回資料「部会第8回会議から第18回会議までの意見要旨(年齢関係)」から行っている。
「保護者」がいなくなる
民法の成人年齢が18歳になると、年長少年は、親権に服さないこととなる。少年法は、第2条2項で、「少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者」を「保護者」というとし、保護者には、付添人を選任したり、審判に出席して少年を支援したり、また、家庭裁判所から訓戒や指導を受ける役割が期待されている。
少年法は、保護者を必ずしも民法上の親権者に限るものではない。しかし、年長少年が成人だとされれば、親権者が存在せず、また、未成年でなければ監護される必要もないため、「現行少年法の基本的な枠組みと不整合」(3頁)であるとする意見がある。
その一方で、少年法は、親権者ではなく、敢えて「保護者」という言葉を使っていること、現実的には、年長少年の多くが親の扶養下にあることから、保護者が存在しなくなるという考え自体が形式的すぎる、とする意見もある。
非行少年は、虐待やいじめといった被害経験を持つがゆえに、そもそも持っている発達の偏りや不適切な養育等とあいまって、非行という問題行動に至る。このような非行少年の脆弱性を支援する人は、多いに越したことはない。保護者は、非行少年たちをもっとも身近で支える人だと概念を整理し直すことは、重要である。また、これを機会に、特に実親から性虐待を受け、家出を余儀なくされた女子少年たちにとって、真の意味の保護者とは誰なのか、ということを考える必要がある。
たとえ、民法上は成人であっても、成長のための「支援」が可能である、と考えることは可能である。どのような支援が非行少年に対して可能なのか、という観点から「保護者」について考え直す必要がある。
「成熟」「未成熟」はクリアカット?
選挙権が年長少年に付与され、「国家の維持形成について責任を有する者と扱われる」(6頁)のであれば、社会的に成熟していると考えられるが、それにもかかわらず少年法において、「判断力が未成熟で国家が健全育成に責任を持つべき者」(6頁)とされることには整合性がない、という意見がある。また、選挙権が与えられるということは、裁判員になる可能性が生じるが、本人は、原則刑事裁判で裁かれることはないことと制度として整合性が取れない、という意見もある。
一方で、選挙権の付与や裁判員としての参加資格は「成熟」した者に与えているのではなく、「国民として勉強するという趣旨」もあるから、少年法とは趣旨が異なる、という意見もある。
法律ごとに、その分野で「成熟」しているかどうかを決めているのが日本の法律であり、そもそも国法は、統一されていない。その原則をどこまで及ぼすかが問題となる。これまで、「成熟」を統一的に「20歳」としてきたことは、この社会が重要な事柄について統一的な年齢を用いると宣言した、と考えることにも一定の合理性がある。しかし、民法の成人年齢の引下げの際に議論されたように、「未成熟」を理由として、消費者としての保護の必要性が若年成人にあるとするなら、年長少年に対しても「未成熟」を理由として保護をする必要性はある、という考え方も十分に合理性がある。
年長少年の行方は?
法制審議会の議論は、残念ながら年齢引下げ論が優勢となっている。日常的に非行少年に関わっている私たちは、年長少年が未成熟であること、引き続き少年としての支援が必要なことを知っている。そのことを前提に、法制審議会の議論を引き続き見守りたい。
以上
【一口メモ:検察官先議主義について】
少年事件は、その全件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。これにより対象となる少年が抱える個別的事情を考慮し、それに見合った対応がとられます(個別処遇原則)。
送致を受けた家裁は、少年鑑別所による資質鑑別や家裁調査官による社会調査という人間行動科学領域の専門的知見をも踏まえて処分を選択します。ただし、「処分」とは、保護観察等の保護処分等であり、家裁自身が刑罰を科すことはありません。
少年に対する刑罰の決定手続は、上記の人間行動科学の知見を踏まえ、家裁が検察官送致の決定を行うことから始まります。つまり、家裁への全件送致主義と併せ考えると、少年にふさわしい処分の判断は、まず検察官が行う(検察官先議主義)のではなく、家裁が行うこと(家庭裁判所先議主義)になっているわけです。
このように少年事件では、家裁が刑事処分相当と判断して検察官送致しなければ刑罰は科されない仕組みであり、少年司法制度では、刑罰よりも保護処分が優先される仕組み(保護処分優先主義)になっています。
(この一口メモは、練馬区保護司会報編集室で付記したものです。)
<注>少年法改正等を審議する「法制審議会ー少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会」の審議経過全般については、こちらから閲覧できます。
<上掲イラストの出所>法務省:いろいろなホゴちゃんとサラちゃんのおへや